渡部達也

講演依頼などの際に必ず主催者さんから略歴を求められるので、めっちゃお手盛りですが、たっちゃん(渡部達也)の略歴を記します。◆◆◆
1965年、
静岡県三島市に生まれる。2歳の時、親が目を離した隙に風邪薬をラムネ菓子と間違えたか、大量に食べ、生死の境を彷徨う。以後、父からは「神様に助けられた命だから、人の役に立つ生き方をするんだぞ」とことあるごとに諭される。◆◆◆3歳からは
静岡県裾野市で育つ。現在も両親は裾野市の実家に在住。遊びの天才児として毎日、夕飯どきまで遊ぶ日々。思春期には何かに躓きそうになると父が掛けてくれる「達也は大器晩成だから。」の言葉に励まされたり、癒されたりしながら、成長。中学時代の恩師の影響で社会科が好きになり、まちづくりに興味を持つようになる。◆◆◆
沼津東高校卒業後、
茨城大学人文学部で現代政治学を専攻。その恩師の教えにより、自分が思い描くまちづくりを実現する手段として
静岡県庁入庁。児童相談所ケースワーカーや富士山こどもの国の設立・運営、国体および全国障害者スポーツ大会の広報などに携わったほか、
(財)静岡経済研究所派遣研究員なども経験。自称(笑)元
県庁の星。◆◆◆先輩・上司にも恵まれ、やりがいのある仕事を数々させていただくも、「行政」という手法によるまちづくりと自分がやりたいまちづくりとの間に次第に溝を感じるようになる。私的な時間を使って、地域での子どもたちの遊び場づくりに関わり、静岡県内8市町で冒険遊び場の立ち上げを支援。障害者野球チームのコーチなどもやらせていただく。◆◆◆それらの経験から、市民だからできることの可能性を感じ、まちづくりという夢を追い求め続けるために、16年余務めた静岡県庁を2004年夏に中途退職。同年秋、
NPO法人ゆめ・まち・ねっとを愛妻と仲間ともに設立。「人にやさしいまちづくり、そして、人がやさしいまちづくり」を掲げて子どもたちの居場所づくりを中心に大人の共感の輪を広げるべく活動中。◆◆◆よく聞かれることについてのブログ記事
「なんで県庁を辞めたの?」◆◆◆現在は、静岡県富士市において、隔週末に開催する
「冒険遊び場たごっこパーク」や平日にあれこれ運営する商店街の空き店舗を活用した
「子どものたまり場・大人のだべり場/おもしろ荘」などの活動を中心に、子どもたちの居場所づくりに取り組んでいる。また、これらの活動を通じて出会う、様々な特性を持つ子どもや生きづらさを抱える子どもと向き合ったり、そうした子どもを持つ親の相談にのることも多い。(一緒に悩むぐらいしかできませんが…。)◆◆◆多彩な講師を招いて、子育て研修会なども企画し、親、地域の人たちとのつながりも築いている。⇒
これまで企画した講演会や勉強会◆◆◆「子どもと遊び」を切り口にした個性的なまちづくり活動は、全国放送で特集が放映されたほか、静岡県内の民放テレビ、ラジオ、新聞でもたびたび特集で取り上げられている。⇒
収録したDVDがあります◆◆◆地域での活動のほか、静岡県内各地はもとより、愛知県、埼玉県、滋賀県、和歌山県、福島県等々全国各地での講演や子どもたちの居場所づくり支援などを通じて、子どもたちに温かなまなざしを向ける大人の輪を全国各地で広げている。◆◆◆富士市での市役所新規採用職員研修、埼玉県入間市での職員研修、御殿場市での市民活動勉強会などで講師を務めたりと、「行政と市民の協働」、「市民活動」などをテーマにした講演なども多い。⇒
これまでの実績・今後の予定◆◆◆ブログ(インターネット)での情報発信にも力を入れており、最近は情報誌からの寄稿依頼も多く、2009年4月から6月には静岡新聞のコラム欄「窓辺」に毎週、計13本のコラムを連載し、多くの反響を得た。⇒
静岡新聞「窓辺」2011年7月から8月には日本教育新聞でコラム連載。同10月からは読売新聞でのコラム連載が始まる。◆◆◆子どもが地域で自由に豊かに遊ぶことが当たり前の社会になり、そして、どんな仕事よりも子育てが最も尊い仕事なんだという認識が社会に広まり、ゆめ・まち・ねっとのような活動が必要なくなる社会を築きたいと夢見る日々。◆◆◆2006年、安藤スポーツ・食文化振興財団(日清食品系)のトムソーヤスクール企画コンテストにおいて、最優秀賞の『安藤百福賞』受賞。2011年、「あしたのまち・くらしづくり活動賞」(読売新聞、NHK、
(財)あしたの日本を創る協会など主催)において、『総務大臣賞』受賞。◆◆◆と、カッコよく綴ってみましたが、いろんな人に迷惑を掛けたり、助けてもらったり、支えてもらったりの半生。そうしたことへの罪滅ぼしや恩返しも含めて、残りの半生を少しでも地域づくり、まちづくり、子どもたちの居場所づくりに費やしていけたらと思っています。もちろん、大海の一滴にすぎないと思いますが。





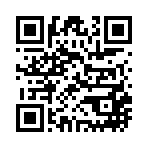

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。